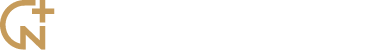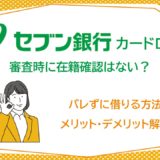所得税と住民税、どちらも働いて給料を貰っている人にとっては馴染み深い税金ですが、給料から天引きされているだけで、どのような違いがあるかは完全に理解していない、という方は多いでしょう。
特に、自分で確定申告をする必要がある個人事業主(フリーランス)には、支払う税金の額や、ひいては自分の社会的信用に関わってくるため非常に重要です。
そこで今回は所得税と住民税について、納付先や課税対象となる年度、税率や計算方法にどのような違いがあるのか、またどのような人が納めるべきなのか詳しく解説していきます。
目次
所得税と住民税の違いとは
所得税と住民税はどちらも国民に納税義務がある税金ですが、次の点で違いがあります。
| 比較項目 | 所得税 | 住民税 |
| 納付先 | 国(国税) | 地方(地方税) |
| 課税の方式 | 申告納税方式 | 賦課課税方式 |
| 課税年度 | 当年の所得に課税 | 前年の所得に課税 |
まず所得税は国に納める税金(国税)ですが、住民税は地方に納める税金(地方税)であり、市区町村・都道府県が納付先となります。
申告方式は、所得税が当年の所得に応じた額を自分で税務署へ納める申告納税方式、住民税は前年の所得額に応じて計算され、市町村から届く納付書を使って納める賦課課税方式です。対象年度の違いに注意しましょう。
所得税と住民税の税率と計算方法
所得税・住民税の税率や計算方法について解説します。
所得税の税率と計算方法
最初は所得税の税率と計算方法を解説します。所得税は、次のプロセスで計算します。
- 総所得金額を求める
- 課税所得を求める
- 所得税額を求める
最初は次の計算式で年間の所得額を求めます。
- 会社員:①総所得金額 = 収入 - 給与所得控除 - 非課税手当
- 個人事業主:①総所得金額 = 収入 - 経費
この計算における「収入」とは何も差し引きされていない素の年間収入額です。会社員の総所得金額を計算する際、収入から非課税手当を差し引くことができます。非課税手当とは、その名のとおり課税されない手当のことです。一例として次の種類があります。
- 通勤手当:公共交通機関の利用額が15万円以下なら非課税
- 日直手当:1回の宿直・日直で4,000円を上限として非課税
- 在宅勤務手当:業務に必要な設備の導入費用や電気代・通信費が非課税
- 資格取得手当:支給した教材費や講習・研修会への参加費用等が非課税
注意点として、資格取得手当は業務に直接関係する資格の取得費用のみ対象となり、個人的に勉強しているものは含まれません。また在宅勤務手当を一括で支給している場合も、非課税にはなりません。
給与所得控除の金額は、非課税手当を除いた給与収入額により変動します。次の表をご覧ください。
| 給与所得の金額 | 所得控除額 |
| ~1,625,000円 | 550,000円 |
| 1,625,001~1,800,000円 | 収入金額×40%-100,000円 |
| 1,800,001~3,600,000円 | 収入金額×30%+80,000円 |
| 3,600,001~6,600,000円 | 収入金額×20%+440,000円 |
| 6,600,001~8,500,000円 | 収入金額×10%+1,100,000円 |
| 8,500,001円~ | 1,950,000円 |
たとえば収入が500万円の場合、所得給与は次のように計算できます。
- 給与所得控除:500万円 ✕ 0.2 + 44万円 = 144万円
- 総所得金額:500万円 - 144万円 = 356万円
次は課税所得を求めます。課税所得の計算では、最初に算出した給与所得から所得控除分を差し引きます。
- ②課税所得 = ①給与所得 - 所得控除
所得控除には「基礎控除」や「社会保険料控除」等の種類がありますが、この点はまた後ほど詳しく解説します。計算例は次のとおりです。
- 事例:給与所得356万円・基礎控除あり
- 計算:356万円 - 48万円 = 308万円
最後の③所得税額の計算は、算出した②の課税所得に税率を乗算した金額から、控除額を差し引きます。
- ③所得税額 = ②課税所得 ✕ 税率 - 控除額
税率と控除額は、課税所得の金額に応じて次のように変動します。
| 課税所得金額 | 税率 | 控除額 |
| 1,000~1,949,000円 | 5% | 0円 |
| 1,950,000~3,299,000円 | 10% | 97,500円 |
| 3,300,000~6,949,000円 | 20% | 427,500円 |
| 6,950,000~8,999,000円 | 23% | 636,000円 |
| 9,000,000~17,999,000円 | 33% | 1,536,000円 |
| 18,000,000~39,999,000円 | 40% | 2,796,000円 |
| 40,000,000円以上 | 45% | 4,796,000円 |
ちなみに実際の税率計算では、基準額を超える部分の税率が高くなる「超過累進課税」方式が採用されます。たとえば課税所得額が700万円の場合、かかる税率は次のとおり変化します。
- 195万円までの部分:5%の税率が適用される
- 195万円を超えて330万円までの部分:10%の税率が適用される
- 330万円を超えて695万円までの部分:20%の税率が適用される
- 695万円を超えて700万円までの部分:23%の税率が適用される
こうして計算した所得税の額には、さらに「税額控除」を適用して直接的に税額を下げられます。税額控除の一例に関しては、後ほど詳しく解説します。
住民税の税率と計算方法

次は住民税の税率と計算方法について解説します。住民税は前年の所得に応じて変動する「所得割」と、納税者から等しく徴収される「均等割」で構成されています。住民税の計算プロセスは次のとおりです。
- 総所得金額を求める
- 課税所得を求める
- 所得割を求める
- 均等割を求める
- 住民税(所得割+均等割)を求める
最初に求める総所得金額の計算方法は、所得税と同様です。
- 会社員:①総所得金額 = 収入 - 非課税手当 - 給与所得控除
- 個人事業主:①総所得金額 = 収入 - 経費
所得税の計算と同様に、給与所得がある会社員は総所得金額に応じた所得控除額を算出して収入から差し引き、個人事業主なら経費を差し引く必要があります。
| 給与所得の金額 | 所得控除額 |
| ~1,625,000円 | 550,000円 |
| 1,625,001~1,800,000円 | 収入金額×40%-100,000円 |
| 1,800,001~3,600,000円 | 収入金額×30%+80,000円 |
| 3,600,001~6,600,000円 | 収入金額×20%+440,000円 |
| 6,600,001~8,500,000円 | 収入金額×10%+1,100,000円 |
| 8,500,001円~ | 1,950,000円 |
次は課税所得を計算します。課税所得の計算方法も所得税と同じです。
- ②課税所得 = ①給与所得 - 所得控除
ここで注意すべき点として、所得控除できる金額の上限は所得税のときと変わります。それぞれの控除額上限については、後ほど詳しく解説します。
次からは所得割と均等割それぞれの税額計算を行います。所得割と均等割の違いは次のとおりです。
- 所得割:前年所得の10%(市町村税6%・都道府県税4%)
- 均等割:納付者から共通で徴収する金額
まず所得割は前年度課税所得の10%であり、さらに「税額控除」を差し引いて求めます。
- ③所得割 = 課税所得額 ✕ 0.1 - 税額控除
ここで差し引ける税額控除の種類については、後ほど詳しく解説します。税額控除がない場合、課税所得の10%が所得割の課税額となります。
続いて均等割は住む地域や自治体によって異なりますが、次の共通ルールがあります。
- ④均等割(市町村民税):3,500円
- ④均等割(道府県民税):1,500円
最後に、算出された所得割の税率と均等割の税率を合算すれば、住民税の算出が完了します。
- ⑤住民税 = ③所得割 + ④均等割
ここまで解説したとおり、税金の計算は複雑です。しかし段階を追ってそれぞれの項目・金額の意味を理解するなら、たとえ会計ソフト等を使用するとしても「なぜその金額になったのか分からない」ブラックボックス状態になるのを避けられます。
所得税と住民税の支払い時期
所得税と住民税の支払時期は、自動的に給与から源泉徴収される会社員と、確定申告する必要がある個人事業主(フリーランス)でそれぞれ異なります。次の表をご覧ください。
| 税金の種類 | 源泉徴収される場合(会社員) | 確定申告する場合(個人事業主) |
| 所得税 | 給与支払月の翌月10日まで | 翌年3月15日まで |
| 住民税 | 給与支払月の翌月10日まで (6月~翌年5月) |
6月・8月・10月・1月 上記月の末日まで |
源泉徴収される会社員は所得税・住民税どちらも給料から天引きされるため、納税手続きは必要ありません。ただし会社員で年間20万円以上の副収入があるなら、上記の個人事業主と同じ期限内での確定申告が必要です。
所得税と住民税で受けられる控除
次は所得税と住民税それぞれに適用できる控除の種類と、控除額の上限について解説していきます。
①所得控除
所得控除とは、課税所得の算出において給与所得から差し引ける金額のことです。所得控除の例は次のとおりです。
| 所得控除の種類 | 控除の詳細 | 所得税 控除上限 |
住民税 控除上限 |
| 基礎控除 | 合計所得金額が2,500万円以下なら 一定額を控除 |
48万円 | 43万円 |
| 社会保険料控除 | 社会保険料(生計同一者を含む)の 支払い分を控除 |
上限なし | 上限なし |
| 生命保険料控除 | 生命保険・介護保険・個人年金保険の 保険料分を一定額控除 |
12万円 | 7万円 |
| 地震保険料控除 | 地震保険の保険料分を 一定額控除 |
5万円 | 2.5万円 |
| 障害者控除 | 本人・生計同一者が障害者の場合に 一定額を控除 |
27万円 | 26万円 |
| 配偶者控除 | 配偶者(納税者)の 合計所得金額に応じて一定額を控除 |
38万円 | 33万円 |
| 扶養控除 | 扶養家族(納税者)がいる場合に 一定額を控除 |
38万円 | 33万円 |
所得控除は、課税額に影響する「見かけ収入」を減らせるため重要です。申告漏れが起きないように注意しましょう。
②税額控除
税額控除とは、算出された所得割の税額から直接差し引ける金額です。税額控除の一例については、次の表をご覧ください。
| 税額控除の種類 | 控除の詳細と上限 |
| 配当控除 | 確定申告において総合所得を適用した配当所得額の2.5%、5%または10%を控除 |
| 外国税額控除 | 二重課税を避けるため海外で課税された額の一定分を控除 |
| 住宅耐震改修特別控除 | 住宅の耐震改修により最大25万円を控除 |
| 住宅借入金等特別控除 (住宅ローン控除) |
借入による住宅の取得等により所得税から控除し、控除しきれない金額はさらに住民税からも最大97,500円を控除 |
| 政党等寄附金特別控除 | 政党等への政治活動資金寄附額から2,000円を差し引いた金額の30%を控除 |
| 認定NPO法人等寄附金特別控除 | 認定NPOへの活動資金寄附額から2,000円を差し引いた金額の40%を控除 |
税額控除は所得控除とは異なり、税額から直接差し引くことが可能です。こちらも納税通知書等で控除額を確認し、申告漏れがないように注意しましょう。
控除を受けるのに確定申告が必要となる人
控除を受けるのに確定申告が必要となる要件について、納税者の立場ごとに解説していきます。
個人事業主やフリーランスの人
個人事業主やフリーランスが控除を受けたいなら確定申告が必要です。確定申告が必要となる条件は次のとおりです。
- 事業所得が基礎控除の48万円を超える場合
- 一時所得が基礎控除の48万円を超える場合
- 株・不動産取引の所得が基礎控除の48万円を超える場合(特定口座を除く)
基本的に重要なのは、所得が「基礎控除を超えるかどうか」という点です。たとえ収入があっても、必要経費を差し引いたあとの所得が48万円以下なら申告は不要です。
ただし事業が赤字の人は、損益通算や赤字の繰り越しが可能となるため、義務化されていなくても確定申告することをおすすめします。また青色申告の特典である「青色申告特別控除」は、確定申告をしないと適用されないため、特別控除を適用する前の金額が48万円に収まっているか確認しましょう。
源泉徴収されている収入があるなら、確定申告により還付金を受け取れる可能性があります。
給与収入が2,000万円を超える人
年間の給与収入が2,000万円を超える会社員は年末調整を受けられないため、確定申告する必要があります。
また、会社員で副業収入がある人も確定申告が必要です。副業による所得が20万円を超えると必須となり、20万円を下回る場合でも住民税の申告が必要です。
所得税と住民税の違いに関するFAQ
最後に、所得税と住民税の違いに関してよくある3つの質問に回答していきます。
所得税や住民税の支払いにクレジットカードは利用できる?
はい、利用できます。所得税は専用サイトから納付できますが、住民税の対応は各自治体により異なります。
たとえば「eLTAX」に対応した請求書が届く地域では、こちらのページから請求書に記載の番号またはQRコードを用いて、クレジットカードによる支払いが可能です。
所得税と住民税の課税対象年度は?
所得税と住民税それぞれの課税対象年度は、次のように異なります。
- 所得税:「当年度」の1月1日~12月31日の所得が対象
- 住民税:「前年度」の1月1日~12月31日の所得が対象
以上の違いにより、新入社員が税金を給与から天引きされる時期も変わります。所得税の天引きは1年目から、住民税の天引きは2年目の6月から開始されます。
所得税が非課税なら住民税も非課税?
いいえ、そうとは限りません。所得税と住民税では、非課税になる条件が次のように異なるからです。
| 比較項目 | 所得税の非課税基準 | 住民税の非課税基準 |
| 会社員 | 103万円 | 100万円 |
| 個人事業主 | 48万円 | 45万円 |
※基礎控除・給与所得控除以外の所得控除や扶養親族の有無、経費、本業以外の収入等は考慮されていません。
どちらも基本的に収入が低い世帯が非課税の対象となりますが、所得税と住民税では所得控除額が異なりますし、生活保護受給者や障害がある方などは住民税が非課税です。個人で状況が大きく変わるため、必ず同時に非課税になるわけではありません。
まとめ
所得税と住民税はどちらも収入にかかる税金のため一緒くたにして考えてしまいがちですが、仕組みや計算方法は異なります。たとえ自動的に天引きされるとしてもその内訳を理解し、いざ確定申告が必要になったとき迷ったり、悩んだりして時間を浪費しないように準備しておきましょう。

税理士として多くの方とお会いした経験上、税金の高さに辟易とした気持ちを抱えている方はたくさんいらっしゃいます。一方で、その税金がどのように計算されているかといった点について、意識の向いている方は決して多くありません。特に会社員の方は、その傾向が顕著であるように思います。税金は給料から天引きされるため、みずから計算したり手続きしたりする機会が失われているためです。
税金について関心を持たれた際には、まず基本的な計算方法から確認されることをお勧めします。そのうえで、自身の状況に応じた対策を検討しましょう。

伴 洋太郎(ばん ようたろう)
税理士 1級ファイナンシャルプランニング技能士
BANZAI税理士事務所 代表
大学卒業後、一般企業や税理士事務所での勤務を経て税理士試験に合格し、2018年にBANZAI税理士事務所を開業。個人事業主や中小法人、給与所得者や相続人を対象とした業務の経験が豊富で、スモールビジネスの立ち上げや個人事業の法人化に数多く携わっている。
HP:BANZAI税理士事務所