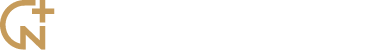キャリアアップを目指す社会人にとって、社労士(社会保険労務士)は魅力的な職業でしょう。
社労士(社会保険労務士)になることで、独立して自分の事務所を開業する道が開かれるだけでなく、企業内での専門職としても活躍することが可能になります。
さらに、他の資格との併用により、扱える業務範囲を拡大し、専門性を高めることが可能です。
しかし、社労士(社会保険労務士)試験は難易度が高く、職業としての適性も重要です。
社労士資格の取得がもたらすメリット、注意すべきポイント、そしてその将来性について詳しく説明します。
目次
社労士資格(社会保険労務士)を取る4つのメリット
社労士(社会保険労務士)資格を取る4つのメリットを紹介します。
高収入を目指せる
大阪大学の研究によれば、開業社労士の約13.5%が年収1,000万円以上を稼いでおり、そのうちの12.6%は1,000万円から3,000万円、0.9%は3,000万円以上の収入を得ています。
これは、正社員の平均年収523万円と比較すると、2倍以上の収入を得る可能性があることを示しています。
高収入を目指す人にとって、社労士は魅力的な職業選択と言えるでしょう。
専門性が高く、独占業務を持つ社労士は、独立開業する道も開かれています。
実際に、社労士を目指す人の中で最も多い動機は「独立して開業できる資格であること」(66.2%)です。
企業に属さずに自分の裁量で仕事をする自由も、社労士としての大きな魅力の一つです。
独立開業できる
社労士(社会保険労務士)は専門的な業務を独占的に行えるため、自営業として独立することが比較的容易な職種です。
企業との顧問契約を通じて安定した収益を確保できるため、年収が1,000万円を超える専門家も少なくありません。
自営業を始めるにあたっては、営業活動やネットワーキングが重要となります。
自己管理のもとで働きたい方には、自分のリズムで業務を進められる独立が適しています。
勤務社会保険労務士として働ける
会計事務所では、社労士(社会保険労務士)は会計士や税理士と共に、便利なサービス提供のために重要な役割を果たします。
労務だけでなく会計処理の知識も身につけることができ、専門性を高めることでキャリアの差別化が図れるでしょう。
一方、一般企業の人事・労務部門では、「勤務労務士」として、採用、教育、評価制度の策定・運用、労務管理など多岐にわたる業務を担当します。
社内での社労士(社会保険労務士)の需要は高まっており、求人も豊富です。
社労士(社会保険労務士)資格は、企業内での人事・労務業務の改善に貢献し、キャリアアップにつながる重要なステップとなります。
まずは、勤務社労士の意味や仕事内容などの基礎知識を押さえておきましょう。
勤務社労士とは?開業社労士・顧問社労士との違い
勤務社労士は、企業に雇用されている社労士(社会保険労務士)で、その企業の人事や労務管理を専門的に扱います。
副業が禁止されている場合、他の企業の人事や労務に対して有償でサービスを提供することはできません。
開業社労士(社会保険労務士)は、勤務社労士(社会保険労務士)とは異なり、自己の事務所を構え独立して業務を運営します。
彼らは企業と顧問契約を結び、クライアントの人事業務をサポートする顧問社労士として活動します。
多くの社労士(社会保険労務士)は、資格取得後にまず勤務社労士として経験を積み、将来的には独立して開業社労士になることを目指すでしょう。
現在、約4万人が社労士(社会保険労務士)として登録されており、その中の約1/3が勤務社労士(社会保険労務士)として企業に属しているとされています。
社労士(社会保険労務士)は様々な形でその専門性を活かし、労働環境の改善に貢献しています。
勤務社労士(社会保険労務士)の仕事内容
勤務社労士(社会保険労務士)は、通常、企業の人事部門や総務部門に配属される専門職です。
彼らの業務範囲は、所属する企業や部署によって異なりますが、一般的には以下のような重要な業務を担当します。
- 従業員の社会保険関連の手続き
- 給与の計算と管理
- 人事評価システムの運用
- 就業規則の更新と管理
- 労働問題への対応と解決
- 人事戦略の策定と実施
- 助成金や補助金の申請手続き
これらの業務を通じて、勤務社労士(社会保険労務士)は企業の人事と労務管理の要となり、組織の円滑な運営と発展に貢献しています。彼らの専門知識と技能は、企業が法令を遵守し、労働者の権利を保護する上で不可欠です。
就職・転職に強い
社労士(社会保険労務士)は、就職や転職市場で非常に重宝される職種です。
社労士(社会保険労務士)資格を有することは、企業にとって望ましい人材の特徴とされ、キャリアアップにも有利に働きます。
社労士(社会保険労務士)としての活動は、開業、社会保険労務士法人の社員、勤務社労士(社会保険労務士、その他のカテゴリーに分けられ、転職先としては主に社会保険労務士事務所、会計事務所、一般企業の人事労務部門が挙げられます。
社会保険労務士事務所は、顧客の労働・社会保険手続き、就業規則の作成、給与計算、行政機関への書類提出代行などを行い、経験に応じてコンサルティング業務も可能です。
ただし、求人数が限られているため、転職活動は広い視野で行うことが推奨されます。
労働関係法令の知識を深めることで自分の身を守れる
労働関係法令は頻繁に改正されるため、その改正を知らないと企業が誤まって労働関係法令に違反することがあります。
社労士(社会保険労務士)の資格を持つ者は、その専門知識を活用して、法律違反を指摘し、法に基づいた適正な運用を企業に促すことが可能です。
社労士(社会保険労務士)でなくても、法律の知識があれば、説得力のある意見を述べることができますが、専門家としての社労士の意見はより重みを持つでしょう。
社労士資格(社会保険労務士)を取るデメリット
社労士資格(社会保険労務士)資格を取るデメリットを説明します。
試験難易度が高い
厚生労働省の最新のデータによれば、令和5年に社労士資格(社会保険労務士)の資格試験に挑んだ人は約5万人で、合格者はおよそ2,700人、合格率は6~7%と報告されています。
これは、同じ国家資格である税理士の合格率18%と比較しても低い数値です。
独学での合格も不可能ではありませんが、推定1,000時間の学習が必要とされ、仕事をしながらの勉強は相当な覚悟を要します。
そのため、多くの受験生が資格学校やオンライン講座(約20万円から)、通信講座(数万円から)などで勉強しています。
受験資格は、特定の学歴、実務経験、所定の試験合格カテゴリーの中のいずれか16パターンの条件を1つ満たすし、関連する証明書類を提出することにより試験を受けることが可能です。
試験は年に1回行われ、学科試験は択一式7科目、選択式8科目で構成されており、労働法令や社会保障法令、労働や社会保険に関連する一般常識など、広範囲にわたる知識が問われます。
資格取得まで時間がかかる
社労士(社会保険労務士)試験合格に必要な勉強時間の目安は1,000時間とも言われており、1日3時間程度の勉強をした場合、1年間程の期間が必要となります。
戦略的に勉強法を検討しておかないと無駄に時間がたってしまいますので、学習プランを検討しておきましょう。
また、予備校やスクールなどに通ったり、通信講座やeラーニングを活用したり、体系だって学習できる勉強法を用意することも大切です。
受験資格を得るには、実務経験2年以上または、講習の修了がマスト
社労士(社会保険労務士)になるための条件として、2年以上の実務経験が必要です。
この経験を持つ方は、追加の手続きなしに直接登録することが可能です。
しかし、実務経験がない方や2年に満たない方は、指定された事務講習を受け、その講習を修了することで初めて社会保険労務士として登録する資格を得ることができます。
経営リスク(独立開業の場合)
独立して開業する際には、自身のスキルと営業活動を通じて顧客を獲得し、1,000万円を超える収入を得る可能性があります。
大阪大学の研究によれば、開業した社労士の約13.5%がこの収入水準に達しています。
その一方では開業社労士(社会保険労務士)の約26.3%は年収300万円未満であることも明らかになっており、中には開業後に期待したほど仕事が増えず、収入が伸び悩むケースもあるのです。
独立開業は、サラリーマンとしての収入を下回るリスクも伴います。そのため、開業後の収入増加を目指す場合、積極的な営業活動が不可欠です。
努力を怠らず、戦略的なアプローチを取ることが成功への鍵となります。
AIに仕事を奪われる可能性
AI技術の進化は、法律専門家の役割にも変革をもたらしています。
社労士(社会保険労務士)の職務においても、AIの適用が検討されており、特定の業務を効率化する可能性があります。
例えば、申請代行や企業の書類作成などの作業は、AIを活用することで簡素化され、専門家の介入が必要な範囲が縮小するかもしれません。
これにより、少ない人員でより多くの案件を処理することが可能になり、1号・2号業務の需要が減少すると予測されています。
一方で、企業のコンサルティングや個別相談などの3号業務は、AIによる代替が難しいとされています。
これらの業務は、個々の状況に応じた細やかな対応や人間とのコミュニケーションが求められるため、AIの現在の能力では対応が困難です。
AIが一般的な書類作成を担うようになっても、コンサルティングや相談業務は引き続き重要な役割を果たすと考えられます。
将来的には、AIと人間が協働することで、社労士(社会保険労務士)の業務はさらに進化するでしょう。
企業が社労士に依頼するメリット
企業が社労士(社会保険労務士)に依頼するメリットを説明します。
より価値の高いタスクにリソースを割ける
社労士への業務委託は、多くのメリットがあります。
特に、社労士(社会保険労務士)に手続きを任せることで、企業の社員は本来の業務に集中することができます。
社員がこれらの手続きに時間を取られることなく、その時間を売上向上に直結する活動に充てることが可能です。
また、労働に関する手続きは複雑で時間を要するため、専門家に委託することで、その分野の知識と経験を活かし、効率的かつ正確に業務を進めることができます。
人件費の削減や業務の効率化が図れるため、経営資源をより価値の高いタスクにリソースを割けることができるのです。
助成金制度の活用が可能
社労士(社会保険労務士)に依頼することで、利用可能な助成金制度をフルに活用することができます。
助成金制度は頻繁に要件が変更されるため、常に最新の情報を把握する必要がありますが、これは担当者にとって大きな負担となり得ます。
本業に専念しながら最新の情報を得て理解することは困難であり、結果として申請期限を逃す可能性もあるでしょう。
しかし、社労士(社会保険労務士)と顧問契約を結ぶことで、助成金に関する最新情報を迅速に入手でき、助成金制度の利用が容易になります。
従業員の満足度向上につながる
社労士(社会保険労務士)を活用することで、労務環境を最適化し、労使間の問題を事前に解決する利点があります。
会社には見えない労務問題が常に存在し、これらが明るみに出た場合、企業の信頼性が損なわれ、重大な損害を受ける可能性があります。
人事労務法は複雑で頻繁に変更されるため、企業が無意識のうちに違反することも少なくありません。
したがって、労務問題の専門家である社労士(社会保険労務士)に委託し、問題が発生する前に対策を講じることが、従業員の満足度向上につながります。
専門家に委託することで労働環境の改善が見込め、従業員のモチベーションアップにつながる
企業が繁栄するためには、従業員の労働環境の質が不可欠です。
良好な労働環境は、従業員のモチベーションアップと生産性を高める重要な役割を果たします。
この目的を達成するために、社労士(社会保険労務士)の専門知識を利用することが、労働環境の改善につながるでしょう。
社労士(社会保険労務士)は、従業員の健康を管理する上での専門家として、企業と労働者の橋渡しを行います。
ストレスの管理や職場での健康促進に関するアドバイスを提供します。
従業員がストレスに直面している場合には、社労士(社会保険労務士)は適切なストレスチェックやメンタルヘルスのサポートを通じて、労働環境の向上に貢献するでしょう。
社労士の需要・将来性
国家資格である社労士(社会保険労務士)は、どのような分野で活躍できるのでしょうか?需要や現状、今後の展望を解説します。国家資格の取得を目指す人はもちろん、社労士(社会保険労務士)として働いている人も、どの分野で需要が増えているのか把握しておきましょう。
社労士(社会保険労務士)の役割は、社会の変化と共に進化しています。
AIの進歩により、書類作成などの基本的な業務は自動化される可能性がありますが、法律の複雑な解釈や個別の労働問題への対応など、専門的な知識と人間の洞察力を要する業務は引き続き社労士(社会保険労務士)の重要な役割として残るでしょう。
また、労働環境の改善やハラスメント対策など、企業が直面する多様な課題に対応するためには、社労士(社会保険労務士)の専門的なアドバイスがますます求められています。
労働人口の減少と働き方の多様化に伴い、効率的な人材管理と労働生産性の向上が重視される中、社労士(社会保険労務士)の役割はさらに拡大していくでしょう。
企業内の人事部門だけでは対応しきれない複雑な人事労務問題に対して、社労士(社会保険労務士)はその専門性を活かし、トラブルの予防から解決までをサポートすることで、今後も重要な存在となり続けることが予想されます。
複雑化する人事労務
企業の人事労務を担当する部署では、社会保険の手続きや就業規則の整備など、幅広い業務を担っています。
しかし、法改正によって知識のアップデートが必要になると、一般の職員だけではなかなか対応ができません。
社会保険や労務の専門家である社労士(社会保険労務士)は、複雑な業務に対応できるスペシャリストとして需要が高まっています。
企業の従業員として働く道だけでなく、コンサルタントとしてアドバイスを提供する役割もあり、活躍できる場所は今後も増えていくでしょう。
個人からの相談業務も増加
社労士(社会保険労務士)は、企業だけでなく個人からの相談にも対応します。
年金の申請代行や保険相談など、個人向けの仕事でも活躍できるのが特徴です。
職場の悩みや労働相談を受け付け、状況によっては企業との話し合いにも対応します。法律・制度に関する専門知識を武器に、個人の課題を解決するサポートが可能です。
特に個人の場合、専門知識がなければ判断が難しい障害年金の申請のために、社労士(社会保険労務士)を頼るケースが多くなっています。
制度が複雑になり、自分での申請や判断が難しくなると、全体的な依頼の増加が考えられるでしょう。
社労士(社会保険労務士)の業務の種類
| 業務の種類 | 内容 | 社労士の独占業務かどうか |
| 1号業務 | 社会保険や雇用保険、労務関係の業務全般にまつわる手続きの代行 | 独占業務である |
| 2号業務 | 雇用契約書、就業規則の制定・改廃、従業員名簿の作成といった帳簿書類の作成 | 独占業務である |
| 3号業務 | 人事労務に関する相談やアドバイスといったコンサルティング業務 | 独占業務ではない |
法律関連の国家資格には、専門的な業務が指定されており、社労士(社会保険労務士)はその中で重要な役割を担っています。
社労士(社会保険労務士)は、労働保険や社会保険の申請書作成と手続き代行を独占的に行うことができ、これらは1号業務です。
また、就業規則や労働者名簿などの書類作成も、社会保険労務士の専門領域である2号業務に含まれます。
一方で、3号業務は独占業務ではないものの、企業や個人へのコンサルティングや相談業務を指し、専門的な知識が求められる分野です。
資格取得後は、これらの業務を通じて、企業や個人の法的な問題解決に貢献することができます。
専門家としての方向性を定め、適切な業務を選択することが重要です。
参考法令として、社会保険労務士法や労働基準法があり、これらの法律に基づいた正確な手続きが求められます。
まとめ
社労士(社会保険労務士)の役割は、企業と個人にとってますます重要になっており、その需要は将来的にも増加すると見込まれています。
AIの進化により一部の業務が自動化される可能性があるでしょう。
しかし、3号業務の企業や個人へのコンサルティングや相談業務は引き続き必要とされます。
社労士(社会保険労務士)資格の取得は、独立開業するだけでなく、就職・転職においても多いに役立つと言えるでしょう。