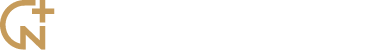老後に必要な資金として「2,000万円」が話題となっていますが、この金額は本当に正しいのでしょうか?
この記事では、独身の方や夫婦で必要な金額をわかりやすく解説し、嘘や実際の問題に焦点を当てています。具体的な計算方法も紹介し、老後に向けた資金計画をしっかりサポートします。
金融庁の金融審議会 市場ワーキング・グループが発表した報告書※によると、退職後の30年間で約2,000万円の資金不足が生じる可能性があるとされています。
この問題に備えるためには、早い段階でライフプランを立て、退職後の資産管理について計画することが勧められます。
具体的には、老後の資金計画を立て、必要な資産をどのように運用し、取り崩していくかをシミュレーションすることが有効です。
※金融審議会 市場ワーキング・グループ報告書「高齢社会における資産形成・管理」P16
しかし、資産形成についての具体的なアプローチが不明確な方も少なくありません。「資産形成」とは、一体何をすれば良いのでしょうか?
そこで、将来に備えて若いうちから実践したい、長期的な資産形成の戦略について、老後2,000万円問題を踏まえながら説明しましょう。
目次
老後2,000万円問題って何?
現代社会では平均寿命が延びており、いわゆる「人生100年時代」と呼ばれる、超高齢社会が到来しつつあります。
しかし一方で、企業の退職金制度は縮小傾向にあります。例えば、大卒の管理職で35年勤続の場合、退職金は1997年の3,203万円から2017年には1,997万円へと4割近く少ないです。
さらに、1992年には企業の92%が退職金制度を有していましたが、2017年にはその割合が80.5%まで低下しています。特に中小企業ほど、退職金制度がない傾向があります。
「老後2,000万円問題」とは、金融庁の審議会が2030年の老後生活で1,300万円〜2,000万円が不足すると試算したことに由来しています。
つまり、退職後の夫婦2人世帯で毎月約5.5万円の生活費が不足するというわけです。ただし、これはあくまでもモデルケースの試算であり、実際の不足額は個人差があります。
そのため、老後にどのように資金を準備するかが大きな課題となっています。長寿化する中で、退職金だけでは老後資金が不足することから、個人による計画的な資産形成が重要になってきているのです。
また、転職が増えたり自営業が増えたりと働き方が多様化する中で、十分な退職金を受給できない人が増えるかもしれません。かつて退職金と年金で老後を過ごせると考えられていた時代とは異なり、自ら老後資金を準備する必要性が高まっています。
年金給付額の増加も期待しにくい昨今、早期から計画的な資産形成に取り組むことが求められます。各人が老後の生活費をシミュレーションし、確実な備えをすることが重要になってきているのです。
必要な老後資金は2,000万円って嘘?
「老後2000万円問題」とは、あるモデルケースに基づいて計算された推定値です。
金融審議会は「高齢社会における資産形成・管理」の文脈で、老後には約2000万円の資金が必要になるという試算を発表しました。
しかし、これは日本の平均的な家庭を例に取り、特定の条件下での貯蓄の取り崩し額を示したものであり、すべての国民に同じ金額が必要であるという意味ではありません。
にもかかわらず、一部のメディアがこの情報を簡略化し、「公的年金だけでは不足する」と報じたことで、国民の間に不安を煽り、社会問題化してしまいました。このような誤解を招く報道は、正確な情報提供の重要性を浮き彫りにしています。
そもそも「老後2000万円問題」に関する情報は、2017年のデータに基づいており、すべての家庭に適用されるわけではありません。また、寿命は個人差があるため、一概には言えません。
2022年からは年金制度に改正が加えられており、2024年現在も変化が続いています。これらの情報を踏まえ、自身に合った老後資金計画を立て、適切な準備を行うことが重要です。
最新の老後資金:夫婦世帯の目安は?
2021年の家計調査年報によると、65歳から90歳までの25年間の老後生活には約555万7,200円が必要とされています。
この試算は、65歳以上の夫婦が対象で、夫は40年間の勤務を経て保険料を支払い、妻は専業主婦であるというモデルケースに基づいています。
これは、定年後の生活費、医療費、その他の経費を考慮した金額であり、将来のインフレや生活水準の変化によって必要な資金は変動する可能性があります。
したがって、個々の生活状況や将来の計画に応じて、より詳細な資金計画を立てることが重要です。
引用元:総務省:家計調査年報(家計収支編)2021年(令和3年)家計調査
| <老後2000万円問題は嘘?夫婦世帯> | |
| [モデルケース] | 夫65歳以上 妻65歳以上 無職世帯 (年金収入のみ) |
| ①公的年金による収入
(平均的な世帯) |
●23万6,576円/月 |
| [内訳] | 年金収入…21万6,519円 その他収入…2万57円 |
| ②老後の生活費(支出)
(平均的な世帯) |
●25万5,100円/月 |
| [内訳] | 食費…6万5,760円 住居費…1万6,608円 光熱水道費…1万9,525円 家具家事用品…1万324円 被服及び履物…4,937円 保健医療費…1万6,159円 交通通信費…2万5,136円 教育費…0円 教養娯楽費…1万9,301円 その他の消費支出…2万5,810円 交通費…2万648円 教育費…0円 教養娯楽費…1万9,301円 その他の消費支出…2万5,810円 交通費…2万648円 非消費支出…3万664円 (社会保険などの支払い) |
| ③収支の差額 | ●1万8,524円/月の赤字 |
| [内訳] | 支出…25万5,100円/月 収入…23万6,576円/月 差額…1万8,524円/月 |
| ④老後25年間の赤字 | ●555万7,200円 |
| [内訳] | 月々の赤字…1万8,524円/月 1年の赤字…22万2,288円/年 25年の赤字…555万7,200円 |
2017年の総務省家計調査年報をもとに算出したところ、老後に必要とされる資金は約2,000万円と推定されます。ただし、これはあくまで一例であり、異なる年度のデータを用いると、必要な資金額は大きく変わる可能性があります。
このことから、老後資金の計画には、複数のデータソースを参考にすることが重要です。
最新の老後資金:単身世帯の目安は?
2021年の総務省家計調査年報によると、65歳で独身の世帯が老後に必要とされる資金は約282万600円です。
2024年には年金制度が大きく変わり、定年は65歳で、90歳までの25年間の老後資金が必要となります。また、年金の受給開始年齢は60歳から75歳の間で、個人の申請によって調整可能です。
| <老後2000万円問題は嘘?単身世帯> | |
| [モデルケース] | 65歳以上独身 無職世帯 (年金収入のみ) |
| ①公的年金による収入(平均的な世帯) | ●13万5,345円/月 |
| [内訳] | 年金収入…12万470円 その他収入…1万4,875円 |
| ②老後の生活費(支出)
(平均的な世帯) |
●14万4,747円/月 |
| [内訳] | 食費…3万6,298円 住居費…1万3,115円 光熱水道費…1万2,585円 家具家事用品…5,034円 被服及び履物…2,914円 保健医療費…8,478円 交通通信費…1万2,187円 教育費…0円 教養娯楽費…1万2,585円 その他の消費支出…13,778円 交通費…1万5,367円 非消費支出…1万2,271円円 (社会保険などの支払い) |
| ③収支の差額 | ●9,402円/月の赤字 |
| [内訳] | 支出…14万4,747円/月 収入…13万5,345円/月 差額…9,402円/月 |
| ④老後25年間の赤字 | ●282万600円 |
| [内訳] | 月々の赤字…9,402円/月 1年の赤字…11万2,824/年 25年の赤字…282万600円 |
2023年と2024年は物価上昇が大きな話題となりましたが、これにより将来の家計調査年報には新たな変動が見られる可能性があります。
老後2000万円問題は現実のものですが、平均的な日本人のモデルケースを基にしたものであり、生活基準が年度ごとに変わることを考慮すると、個人の状況に応じた慎重な判断が求められます。
[参考]
総務省:家計調査年報(家計収支編)2021年(令和3年)家計調査
なぜ老後資金として2,000万円必要だと言われているのか
「老後2,000万円問題」について、なぜ退職後の資金としてその金額が必要とされるのか、3つのテーマから深く掘り下げていきましょう。
二人暮らし世帯は毎月2万円が不足
2021年の総務省のデータによると、65歳以上の無職の夫婦世帯の月平均実収入は約23.7万円、可処分所得は約20.6万円でした。
これに対し、消費支出は月平均約22.4万円で、結果として毎月約2万円の赤字が生じています。この状況が続けば、65歳から95歳までの30年間で約480万円の資金不足になると予測されます。
引用元:総務省「家計調査年報(家計収支編)2021年(令和3年)Ⅱ総世帯及び単身世帯の家計収支」
もし不足額が少なければ、適切な貯蓄や金融商品への投資によって、生活に困ることはないかもしれません。しかし、介護が必要になるなど予期せぬ出費が発生する可能性もあります。
そのため、「2,000万円がなければ生活できない」と断言することは難しいです。
ゆとりある生活をしたいなら毎月15万円が不足
ゆとりのある老後を望むなら、その準備は異なるアプローチが必要かもしれません。
生命保険文化センターの研究によると、快適な退職生活には、基本的な日常生活費に加えて、平均で月額14万8千円が必要だとされています。
引用元:公益財団法人生命保険文化センター「老後の生活費はいくらくらい必要と考える?」
ゆとりある生活を目指す場合、毎月の追加収入として15万円が必要だと考えられます。この追加収入は、旅行、レジャー、日々の生活費の向上、趣味や自己啓発に充てられることが多いです。
95歳まで生きると仮定すると、65歳からの30年間で約5,400万円が必要になります。
2,000万円では明らかに不足しており、病気や怪我の治療費、介護費用などの予期せぬ出費も考慮すると、さらに多くの資金計画が求められます。
生活スタイルによっては2,000万円では足りないかも
老後に必要な資金は個々の生活スタイルによって大きく異なると言えます。例えば、質素な生活を心がける場合、基本的な年金給付金に少し加えるだけで足りるかもしれません。
一方で、年に一度の旅行や家族の大切なイベントへの援助を望むなら、2,000万円では足りないことが予想されます。
そのため、理想的な老後生活を実現するためには、どのような生活を送りたいかに応じて、必要な資金額も変わってくるのです。
老後資金を残しておくためのポイント
老後資金を残しておくためのポイントを説明します。
ライフプランを作成する

画像引用元:Officeテンプレート「ライフマネープランシート」
安定した老後を送るためには、ライフプランの策定が重要です。将来にわたって資金が不足しないように、年ごとのキャッシュフローを計算し、貯蓄や収入、支出を見積もると良いでしょう。
これには、日常の生活費だけでなく、旅行や車の更新、ローンの返済などの一時的な出費も含まれます。
ライフプランは、結婚、出産、住宅購入などのライフイベントを通じて変化する生活スタイルを、財務面で具体的に計画することです。
例えば、「2年ごとに海外旅行を楽しみたい」「子どもの結婚式には援助を提供したい」といった老後の夢を実現するためには、それらを計画に組み込むことが大切です。
ライフプランを立てることで、老後に必要な貯蓄額を把握し、目標達成のための戦略を立てられます。また、潜在的な問題点を事前に特定し、対策を講じることも可能になります。
生活費の見直し
経済的な安定を維持するためには、生活費の見直しが不可欠です。65歳を迎えて年金を受給しても、その金額だけで毎月の支出を賄うのは困難です。
節約は必要ですが、生活の質を保ちながら無駄遣いを避け、賢く貯蓄を管理することが重要です。快適な生活を送るためにも、適切な費用管理を心掛けましょう。
定年退職してもバイトやパートなどで収入を得る
長期間にわたって働き続けることは、退職後の資金不足を防ぐための効果的な手段です。
定年退職後も職場で働くための制度や、新たな職を見つけるための支援がある場合は、これらを利用することが賢明です。さらに、持っている資格やスキルを生かし、自分のビジネスを立ち上げることも、将来の選択肢として考えられます。
年金の受け取りを先延ばしする
公的年金制度では、65歳からの受給開始が基本ですが、受給開始を75歳まで延期する選択肢があります。延期期間が長ければ長いほど、受け取る年金は増え、1ヶ月ごとに0.7%ずつ加算されます。例えば、75歳まで延期すれば、年金は最大で84%増額されます。
65歳で収入がある場合、年金受給の延期を考えることは、将来の年金総額を増やし、老後の資金計画に有利です。
老後のために資産運用を行う
老後資金を確保する方法として、長期にわたる積立投資も検討に値します。例えば、毎月3万円を年4%の利回りを前提に30年間運用した場合、最終的な積立金額は約2,082万円に達します。
このように2,000万円を上回る老後資金の確保が可能となる可能性があります。ただし、投資にはリスクが伴うことに留意が必要です。
元本保証はなく、運用実績によっては想定を下回る可能性もあります。資産運用に際しては、リスク許容度を踏まえた上で、長期的な視点に立った投資計画を立案することが賢明でしょう。
老後のために資金を作ろう!おすすめの資産運用
老後資金作りにおすすめの資産運用を紹介します。
NISA・つみたてNISA
2024年からスタートした新NISAは旧NISAと何が変わったかから説明します。
| 旧NISA | 新NISA | |||
| つみたてNISA | 一般NISA | つみたて投資枠 | 成長投資枠 | |
| 併用の可否 | 併用不可 | 併用可 | ||
| 年間投資枠 | 40万円 | 120万円 | 120万円 | 240万円 |
| 非課税保有期間 | 20年間 | 5年間 | 無期限 | 無期限 |
| 非課税保有限度額 | 800万円 | 600万円 | 1,800万円
内数:1,200万円(成長投資枠) |
|
| 口座開設期間 | 2023年まで | 2023年まで | 恒久化 | 恒久化 |
| 投資対象商品 | 長期の積立・分散投資に適した一定の投資信託 | 上場株式・投資信託等 | 長期の積立・分散投資に適した一定の投資信託 | 上場株式・投資信託等 |
| 対象年齢 | 18歳以上 | 18歳以上 | 18歳以上 | 18歳以上 |
引用元:金融庁「新しいNISA」
2024年1月から新しいNISA制度が開始されました。これに伴い、従来の一般NISAとつみたてNISAは一本化され、新NISA内で以下の2つの投資枠に再編成されています。
- つみたて投資枠
- 成長投資枠
一方で、ジュニアNISAは2023年をもって制度が終了しました。新制度への移行により、年間投資可能額や非課税保有期間など、以下の大幅な変更が行われています。
- 年間投資可能額(非課税投資枠)の拡大
- 非課税保有限度額の増額
- 非課税保有期間の無期限化
- NISA口座開設期間の無期限化(恒久化)
このように新NISAでは、より利用しやすい制度設計が行われ、中長期の資産形成をサポートする内容となっています。
iDeCo
| 税制優遇の内容 | |
| iDeCo | 利息・運用益が非課税で、受取時も税制優遇あり さらに掛金が全額所得控除となる |
iDeCo(個人型確定拠出年金)は、将来の安定した生活を目指す個人が自らの資金を管理し、投資信託や保険、定期預金などの金融商品を通じて資産を形成するための制度です。
この制度は、掛金の所得控除による節税、運用益の非課税、そして受給時の税制優遇という、3つの大きな税金上の利点を提供します。
NISAと同様に非課税のメリットを享受できる一方で、iDeCoは所得控除や退職金受給時の控除といった税制上の特典も加わり、これがiDeCo独自の魅力となっています。
財形年金貯蓄
財形年金貯蓄は、勤労者財産形成促進法に基づき運営される、サラリーマン向けの資産形成手段です。給与から直接控除されるシステムにより、定期的に貯金を行うことが可能です。
この制度は55歳未満の勤労者を対象としており、60歳からの5年以上20年以下の期間で年金を受け取れます。また、住宅財形と併用することで、最大550万円までの貯蓄に対する利息が非課税となります。
引用元:厚生労働省 財形貯蓄制度
投資信託
投資信託は、多くの投資家から資金を集め、その資金をファンドマネージャーが集中管理し運用する金融商品です。
各投資信託は特定の運用ルールに従い、ファンドマネージャーが投資方針や対象を選定します。主に、インデックスファンドとアクティブファンドの二つのタイプがあり、前者は市場の平均的な動きに追従し、後者は平均を超える収益を目指します。
日本では約6,000の投資信託があり、銀行や証券会社を通じて購入でき、通常は1万円からの投資が可能です。投資信託によって初期投資額や最低購入単位が異なります。
専門家による運用と分散投資のメリットがある一方で、ファンド手数料などのコストも発生します。
個人年金保険
個人年金保険は、老後の資産形成に役立つ生命保険の一種です。個人年金保険には、個人年金保険料控除という税制優遇があります。(※)
※2012年以降の契約の場合。2011年以前の契約は旧制度が適用されます。
この控除を利用すると、所得税や住民税の負担を減らすことが可能です。ただし、控除を受けるには、個人年金保険料税制適格特約という条件を満たす必要があります。
この特約は、保険料の支払い期間が10年以上で、年金受取人が被保険者本人であることなどが条件です。一時払いの個人年金保険は対象外ですので、ご注意ください。
不動産投資
不動産投資は、投資家が物件を購入し、それを他人に貸すことで賃貸収入を得る手法です。この投資の利点は、収入源を比較的安定させることが可能である点です。
しかし、入居者が見つからない場合、空室が長期化し計画が狂う可能性があります。さらに、地震や火事などの自然災害のリスクも考慮する必要があります。
資産運用の際の注意点
資産運用の際の注意点を説明します。
元本割れのリスクがあることを理解する
資産運用を行う際には、投資元本が減少するリスクが伴います。多くの金融商品は元本保証がなく、市場の波によって資金が目減りすることもあり得るのです。
ただし、価格が下がっている時に売却しない限り、損失は仮定のものに過ぎません。長期間にわたって市場を見守れば、価格の回復により利益を得る可能性もあります。
特に配当や分配金を提供する金融商品を選べば、これらの収入が積み上がり、最終的な収益を向上させることが可能です。
重要なのは、短期的な市場の変動に動じず、長期的な目標に集中することです。
急な出費に備えて全額を投資に回さない
利益が出た際には、さらなる利益を目指して投資額を増やすことが考えられますが、損失が発生した場合には、それを取り戻すためにさらに資金を投じることもあります。
これは人間の本能的な反応ですが、投資に充てる資金が過多になると、予期せぬ支出に対応できなくなるリスクがあります。
日常生活に必要な資金が投資計画に影響を受けることは避けるべきです。不測の事態で資産を売却することになれば、目標としていたリターンを達成できない可能性があるだけでなく、損失を確定させることにもなりかねません。
また、日々の生活に支障を来たすほどの資金を投資に回すことはリスクが高い行為です。資産運用は、生活費に影響を与えない範囲の余剰資金で行うべきです。
資金の配分は慎重に行い、生活資金と投資資金を明確に区別しましょう。
必要な老後資金は生活レベルで異なる
夫婦2人を前提にした老後の日常生活費は「平均221,000円」となっていますが、これは最低限の生活レベルを維持するための金額になります。
これはあくまでもひとつの目安でしかないので、賃貸か持ち家かなど個別の環境の違いや生活レベルによって実際に必要な老後資金は大きく異なるでしょう。
趣味や付き合いなどを想定した「老後のゆとりある生活」をイメージするときには、この金額に10〜15万円の上乗せが理想として、毎月361,000円が平均値となります。
さらに老後は病気のリスクも高まるため、治療費や入院費用、さらに介護の費用という項目も忘れてはいけません。たとえ趣味や浪費を控えてお金のかからない生活を心がけていたとしても、生活レベルは望まず急転する可能性もあるのです。
理想とする生活レベルだけでなく、体調の変化なども見据えた老後資金の設定を行っておきましょう。
投資商品のリスクを理解し分散投資を心がける
投資商品にはそれぞれの特性に応じたリスクがあるため、分散投資によるリスク軽減を心がけておくようにしましょう。
たとえば株式投資や債券投資においては、保有している銘柄の値下がり・破たんなどによる元本割れのリスクがあります。
またFX(外国為替証拠金取引)や仮想通貨は高いレバレッジ効果で少額から大きなリターンを得られる反面、資金を一瞬にして失う危険性も高めてしまうのです。
不動産投資では資産としての形は消えないものの、物件の老朽化による修繕費用のコストから家賃の相場下落や滞納・空室リスクといったものが発生します。
大切な老後資金を確実に作っていくためにも、投資商品ごとの特性をよく理解した分散投資は欠かせません。
若い人は長期投資ができる商品に投資するのがおすすめ
比較的年齢が若い人には、焦らずにコツコツと増やせる長期投資の商品がおすすめです。
長期投資と呼ばれるのは10年単位の期間で投資するもので、おすすめの商品には「株式投資・投資信託・債券投資・純金積立」などいろいろなものがあります。
一般社団法人投資信託協会の行った調査によると、過去40年間の東証1部銘柄の投資収益は10年以上の長期で保有するほど安定するという結果を出しています。
若いうちから長期投資を始めておけば毎月の額は少なくとも積立資金は大きくなっていき、さらに期間による収益にも期待できるということです。
まとめ
金融庁の市場ワーキング・グループが示した「老後に約2,000万円の資金が不足する」という試算は、多くの人々に不安を与え、「老後2,000万円問題」として広く知られるようになりました。
この試算は一例に過ぎず、実際の金額は個人によって異なるものの、メディアの注目を集めています。
日本では退職金の減少と年金給付額の増加が見込みにくいため、早期からの資産形成が重要です。非課税の投資制度であるNISAやiDeCoなどの活用を検討してみましょう。