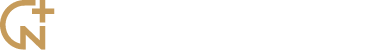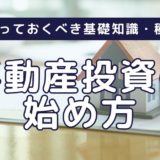2024年からスタートした「新NISA」は投資家だけでなく、数年後・数十年後の未来を見据えて資産形成したい人にとって魅力的な制度ですが、飛びつく前にメリット・デメリットを正確に把握することは重要です。
旧制度である一般NISAやつみたてNISA、ジュニアNISAとの違いや、新NISAに変わったことでできるようになったこと、できないことについて理解するなら、単純に知識や経験が足りないことで可能性が高くなる「元本割れ」のリスクを下げ、自分にとって最適な選択を行うことができます。
わかりやすいメリットだけでなく、新NISAをおすすめしない人の特徴やデメリット、改悪と言われている部分に関して正しい知識を身に着け、これからの資産運用に役立ててみましょう。
目次
NISAの概要を解説
最近よくテレビやSNSで「NISA」という言葉を聞くようになりましたが、それが何なのか分からない、または漠然としたイメージしかなく、メリットやデメリットが分からないという方も多いでしょう。そこでまずは「NISAとは何か」という点について、制度ごとに詳細を解説していきます。
一般nisaとは
一般NISAとは「NISA(少額投資非課税制度)」の一つであり、次のような特徴があります。
- 最長5年にわたり非課税で金融商品に投資・運用できる
- 年間の非課税投資枠は120万円
- 対象商品は株式・投資信託・ETF・REITなど
- 現在新規購入は停止されている
一般NISAにおいて非課税になるのは投資により得た利益であり、本来発生する20%の税金がカットされます。
たとえば投資で20万円の利益が出た場合、普通なら4万円が課税されるため16万円しか受け取れません。しかし一般NISAを介した投資なら、20万円満額を受け取れることになります。
ただし、際限なく非課税になるわけではありません。限度は「年間120万円まで」と決まっており、上限を超えた分は課税されるため確定申告が必要です。
一般NISAの制度は2014年に開始しましたが2023年で終了しており、2024年以降は新たな拠出ができません。しかしすでに購入した商品の運用は2027年まで可能です。
つみたて積立nisaとは
つみたてNISAは一般NISAと同じく「NISA(少額投資非課税制度)」の一つであり、次のような特徴があります。
- 最長20年にわたり非課税で金融商品に投資・運用できる
- 年間の非課税投資枠は40万円
- 運用できる商品は金融庁が認可したものに限定される
- 現在新規購入は停止されている
つみたてNISAも一般NISAと同様に、金融商品の投資・運用で得た利益が非課税になります。ただし年数と年間の拠出上限に大きな差があり、つみたてNISAは年間の拠出額が低い代わりに、20年という長期での運用が可能な仕組みとなっています。
ただしこちらも「新NISA」への切り替えに伴い、2023年に新規購入受付は終了しています。すでに運用を開始している商品は、非課税期間の上限である20年後、つまり2043年まで運用が可能です。
ジュニアnisaとは
ジュニアNISAも一般NISAやつみたてNISAと同じ少額投資非課税制度の一つです。次のような特徴があります。
- 最長5年の非課税期間
- 年間で投資できる金額の上限は80万円
- 0〜10歳の未成年者(現在は18歳以上で成年)が対象
- 払い出しが可能になる年齢は18歳
ジュニアNISAは未成年を対象とした制度であり、親などの法定代理人の同意のもと加入することができます。現在の新NISAは18歳以上が対象であるため、2023年末の終了をもって、当制度は実質的に廃止されたと言えます。
既存の運用商品に関しては2027年まで運用が可能です。すでにジュニアNISAの新規購入はできないため、代わりに新NISAへの移行を検討しましょう。
新nisaとは
一般NISA・つみたてNISA・ジュニアNISAに代わってできた制度が、2024年から始まった「新NISA」です。この制度には、次のような特徴があります。
- 非課税期間が無期限になる
- 非課税投資枠が1800万円に拡大される
- 「つみたて投資枠」と「成長投資枠」が新設される
- 口座開設期間が無期限になる
上記のとおり、新しく始まったNISAはルールが緩和され、より多く、長期での投資・運用が可能となりました。非課税で運用できる期間は無期限になり、投資の上限も1800万円と大きく拡大しています。
以前の一般NISAは「成長投資枠」に、つみたてNISAは「つみたて投資枠」にそれぞれ制度の一環として取り込まれています。それぞれの特徴は次のとおりです。
- 成長投資枠:年間120万円まで投資可能、保有可能限度額は累計1,800万円まで
- つみたて投資枠:年間240万円まで投資可能、保有可能限度額は1,200万円まで
成長投資枠は株式・投資信託・ETF・REITに投資が可能であり、この点は以前の一般NISAと共通しています。ただし監理・整理銘柄や信託期間が20年に満たない投資信託などは成長投資枠でも購入できません。
それに対してつみたて投資枠は、従来のつみたてNISAと同様に金融庁が認可した比較的信託報酬が低い商品に限定されます。国内では現時点で株式型が154本、資産複合型が127本対象となっています。
自由度が高い成長投資枠にするか、長期を見据えたつみたて投資枠にするかは個人の判断です。新NISAをはじめる前に投資目標の設立やリスクの理解を行い、必要な場合には専門家に相談することをおすすめします。
NISAのメリットデメリット
次はNISAのメリットとデメリットについて解説していきます。
NISAのメリット
NISAのメリットとしては、次の点が挙げられます。
- 資産形成が効率化できる
- 運用益や配当が非課税になる
- 資金の用途が限定されない
NISAで金融商品を運用すると、購入額と売却額の差額による運用益が発生し、さらにその運用益が追加で利益を生み出します。この「複利効果」の仕組みによって、貯金や保険商品よりも大きく高い効率での資産形成が可能です。
投資による資産形成は、長期にわたるほどリスクが小さくなります。もともとNISAも長期運用が大前提の制度であるため、短期で大きなリターンを期待する投資家には向いていませんが、20年または30年以上、老後の生活までを見据えている方にとっては良い制度です。
また運用益・配当はこれまで通り非課税となり、確定申告も不要です。また金融商品はいつでも売却可能であり、使用用途も自由で制限されていません。
NISAのデメリット
NISAのデメリットとしては、次の点が挙げられます。
- 損益通算ができない
- ロールオーバー・旧NISA口座の資産移動は不可
まず、NISAはNISA口座で損失が出ても、他の口座の利益で埋め合わせる「損益通算」ができません。これは、NISA口座で損失が生じても税務上は「ないもの」扱いになるからです。
そもそも利益に課税されていない時点で、損失が出たとしても例外的に税務上の対象にならないことは容易に理解できます。
また新NISAは翌年分の非課税投資枠に資産を移管する「ロールオーバー」ができません。
そもそも非課税期間が無期限であるため当然なのですが、ロールオーバー不可は旧NISAを運用している人にも当てはまります。一般NISA・つみたてNISAの資産を新NISAに移行することはできません。
NISAをぶっちゃけやめた方がいい人、やるべき人
次はNISAとやめた方が良い人とやるべき人の特徴についてそれぞれ解説していきます。
やめた方がいい人の特徴
NISAをやめた方がいい人の特徴は、次のとおりです。
- 余剰資金が捻出できない人
- 短期で儲けることが目的の人
- 一定のリスクを許容できない人
余剰資金が捻出できない人
NISAは口座によっては最低100円という少額から投資が可能ですが、収入が少ないため生活そのものに困っており、余剰資金がないという人にはおすすめできません。あくまでNISAは資産を効率的に増やせる「手段」でしかなく、0から100を生み出せるものではないからです。
もし見切り発車しても、早期に拠出が途絶えてしまうようでは意味がありません。あくまで新NISAは長期運用を前提とした資産形成方法であり、「数ヶ月で◯◯円稼げる」という類のものではないからです。
短期で儲けることが目的の人
同様の理由で、短期投資による大きな利益を目的とした人にも向いていません。株式等の金融商品は日々その価値が変動しますが、価格が下落したときに売却すると単純に損失となります。
年間の投資枠は「360万円まで」という制限もあるため、投機が重要な短期売買にはそもそも向いていないのです。
一定のリスクを許容できない人
NISAは効率的に資産形成が可能ですが、利益が出ることを保証するものではありません。インフレリスクだけでなく、リーマンショックのような出来事が発生すると金融商品の価値が急落し、大きく元本割れする可能性もあります。
これは金融商品を売買する投資すべてに当てはまることですが、リスクがあることを許容できない人、または認識したくない人はNISAをはじめるべきではありません。
やるべき人の特徴
NISAをやるべき人の特徴は、次のとおりです。
- 老後のために資産を増やしたい人
- 多めの余剰資金がある人
- 少額投資したい人
老後のために資産を増やしたい人
NISAは老後資金を用意したい人にとって高いメリットがあります。不自由なく老後を過ごすためには少なくとも2,000万円が必要だと言われていますが、もし安定した収入があっても、預けておくだけではほとんど増えない貯蓄だけで2,000万円を貯めるのは簡単ではありません。
しかしNISAなら、若くして20代から老後のための蓄えをはじめることが可能です。しかも投資により資産を効率よく増やせるので、モチベーションも保ちやすいです。
多めの余剰資金がある人
NISAは、貯蓄とは異なる余剰資産がすでに多くある人にもメリットが大きいです。NISAは株式投資やFX投資等よりもハードルが低いですが、投資における価格変動リスクがなくなるわけではなく、大きな損失を出すリスクを認識しておく必要があります。
余剰資産の多さは心の余裕を生み出し、長期的な視点で考えられるようになるため重要です。
少額投資したい人
一口購入するために数万円以上の資金が必要になる個人での株式投資とは異なり、NISAは最低100円から投資が可能です。そのため資産形成はしたいものの投資に不安があり、最初は少額で始めたいと考えている人に向いています。
【損する可能性は?】NISAで元本割れするリスク
次はNISAにおける元本割れリスクについて解説していきます。
元本割れとは
元本割れとは、最終的な資産額が投資額を下回ることです。たとえば100万円投資して最終的な資産額が200万円なら、100万円の利益が出ているため全く元本割れではありません。
しかし100万円投資した結果、最終的な資産額が「90万円」であった場合は、100万円投資したにもかかわらず10万円の損失が出ているため、元本割れが発生しています。
NISAも常に価格が変動する金融商品を運用するため、元本割れのリスクは存在します。だれも将来を正確に予測できないため、たとえ投資のプロであっても、手元にある金融商品の価値が半減するようなことは起こらないと断言することは不可能です。
元本割れするリスクと後悔しないための対策
NISAで元本割れする主な原因は「短期で運用をやめてしまうこと」です。すでに解説したとおり、NISAは長期運用が前提の制度です。金融商品の運用により利益が出ると、それを元手に投資することでさらなる利益を生み出すことができます。
しかし一時的に株式が暴落した、などの理由で売却していては福利効果を得られません。単純に十分な回数の再投資が行えず、利益が蓄積されないからです。結果的に、損失による元本割れという結果だけが残ることになりかねません。
そのためNISAをはじめるなら、少なくとも5年・10年先のことを見据えた計画を立てるようにしましょう。たとえば価値の上下にかかわらず毎月一定額を投資することで、「ドル・コスト平均法」による単価の低下、長期的な利益の安定化を図ることができます。
よくある質問
最後は、NISAに関して3つのよくある質問に回答していきます。
今NISAの口座講座開設をするのは待つべき?
旧制度の一般NISA・つみたてNISAはすでに制度としては終了し、2024年から完全に「新NISA」へ切り替わっているため、待つ必要はありません。ただし口座開設は一人につき一口座しか作れない点や、証券会社によって開催しているキャンペーンの適用期間や内容が異なる点には注意が必要です。
運用して5年後のシミュレーションはできる?
いくつかの金融機関は、投資額や運用年数、運用商品に応じたシミュレーションツールを提供しているため、申し込む前に利用できます。
しかしあくまでシミュレーションであるため利益が一定であったり、考慮するべきリスク要素が不十分なこともあるため、あくまで参考程度にとどめておくべきです。
70代でもNISAを始めるべき?
保有期間が無制限であることや利益が非課税になることの利点は年齢に関係ないため、70代からでもNISAをはじめることは可能です。しかし現実としては次の問題があります。
- 非課税で保有できる期間は15~20年程度になってしまう
- 運用できる年数が短いと元本割れするリスクが高くなる
平均寿命を考慮すると、70代からNISAをはじめる方が運用できる期間は長くても15~20年程度です。
そのため20代・30代からNISAをはじめた人と比較して複利効果が薄いため積み上げられる利益が少なく、元本割れするリスクも高いことを理解しておく必要があります。
まとめ
新NISA制度がスタートして多くの人の関心が集まっている今だからこそ、この制度のメリットやデメリット、有用性やリスクについて正しい認識を持つことは重要です。
このタイミングで、改めて自分は将来の備えができているか、NISAをはじめることでどのような未来が構築可能かシミュレーションし、正しい決定ができるように備えておきましょう。