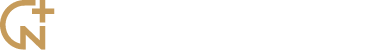会社員やサラリーマンの人は所属している企業が納税処理をおこなっているため、節税について意識していない人が多くいます。
所得税や住民税は給料から天引きで引かれているため、どうしようもないと思っている人も多くいますが、実は税金の仕組みを理解して控除制度を利用することで、節税ができます。
節税を行うためには、いくつかの条件があるのでしっかり確認をして、節税を試してみましょう。
会社員やサラリーマンでも、簡単にできる節税方法を紹介していきます。
目次
会社員(サラリーマン)が支払わなければいけない税金
会社員が支払わなければならない税金をご紹介します。
- 所得税
- 住民税
まず税金として支払わなければならないのは、上記の所得税と住民税です。所得税は、所得に応じて課税される税金です。住民税は居住している市区町村に収める税金で、前年の所得に応じて全国一律10%が課税されます。
税金以外で会社員の給料から約15%程度天引きされているのが、社会保険料です。社会保険料は以下の3つが挙げられます。
- 雇用保険料
- 健康保険料
- 厚生年金保険料
雇用保険料は、育児休業・病気などで休業した時の手当の支払いや、失業した時の保障などが雇用保険料から賄われています。健康保険証を利用する際、窓口で3割負担で済むのは、会社員が健康保険料を納めているおかげです。
厚生年金保険料は、老後に給付される年金制度で会社員の場合は、給料に保険料率を掛けた金額が天引きされます。等級ごとに分類されていて、等級に応じた税額が計算されます。
上記の5種類が会社員(サラリーマン)が支払わなければいけない税金です。
会社員やサラリーマンでもできる節税対策11選
会社員やサラリーマンとして働いている人は、企業側が給料から社会保険料や税金などを徴収するため、節税方法を知っている人は少ないのが現状です。
しかし、サラリーマンでも活用できる節税対策はあり、確定申告を行うことで税金が戻ってくる可能性もあります。
はじめに、会社員やサラリーマンでもできる節税対策を紹介していきます。
- ふるさと納税
- iDeCoやNISAを始める
- 税金の支払い方を変える
- 生命保険料控除・地震保険料控除
- 医療費控除
- 住宅ローン控除
- 離婚または死別した時
- 災害・盗難にあった時
- 株取引で損をした時
- 特定支出控除の特例を活用する
- 共働き夫婦は扶養控除のつけ方に注意する
節税の恩恵を受けるには確定申告が必要ですが、必要な書類も少なくて手続きも簡単なため、だれでも簡単に実践できます。
節税対策1:ふるさと納税
会社員の節税対策で一番有名なのがふるさと納税です。全国各地の自治体の中から、自分の好きな自治体に寄付することで、寄付金控除が受けられます。
ふるさと納税を利用すると、地方自治体から寄付金のお礼が受け取れるため、人気の高い制度となっており、利用している方も多い制度です。
ふるさと納税は、会社員やサラリーマンの方でも簡単にできる節税方法としても有名で、以下の条件を満たした場合、所得税を払い過ぎている場合は、お金が返ってくる場合があります。
- 自己負担額の2,000円を除いた全額
- (総所得金額等×40%)-2,000円
上記のどちらかに当たる場合は、還付金を受け取れます。また、ふるさと納税は住民税の税額控除もあり、寄付を行った翌年から支払う住民税が軽減されます。所得税と住民税の控除を受ければ、大きな節税効果が期待できます。
会社員などの給与所得者で、寄付先が年間5件以下の場合は、「ふるさとワンストップ特例制度」が適用されるため、確定申告が必要ありません。
6自治体以上に寄付をした場合は、給与所得者でも確定申告が必要になり、医療費控除や住宅ローン控除などを受けられないデメリットもあります。
節税対策2:iDeCoやNISAを始める
会社員やサラリーマンの節税方法として注目を集めているのが、iDeCoやNISAです。iDeCoは、個人型DCのことを示していて、国の年金だけでは足りない老後資金を積み立てていくサービスです。
老後の資金不足に備えて利用する方が多く、口座を開設した後に毎月自分で掛金を設定して、積み立てて行きます。掛け金自体が所得控除の対象になるため、その年の所得税と翌年の住民税を抑えられることに加え、節税された所得税は年末調整に上乗せされ戻ってきます。
一方で、住民税は翌年5月から給与天引きされる金額が安くなります。さらに、iDeCoを運用しているときに増えた分のお金には、税金が発生しません。
退職金や公的年金を受け取る際の税制にも適用されるため、税金負担が軽減される場合もあります。NISA口座を作ると、年間で120万円、5年間で最大600万円までの投資額が非課税となる制度で、NISAを使った投資による利益は、5年間非課税です。
つみたてNISAの場合は、年間で40万、最高で20年の投資額が非課税になる新しい制度です。
節税対策3:税金の支払い方を変える
会社員やサラリーマンの中には副業を行っている人もいますが、副業などで得た収入を確定申告した後に、納税しなければいけません。この納税方法の支払いにクレジットカードを利用することで、クレジットカードのポイントが貯められます。
各種地方税に関しては地方自治体によって異なりますが、これまでもクレジットカードでの支払いが認められているものもたくさんあります。
2017年からは所得税などの国税もクレジットカード支払いができるようになったため、少額ではありますが、現金と同じように利用できるポイントも多いため、貯めていきましょう。
節税対策4:生命保険料控除・地震保険料控除
生命保険や地震保険に加入している人は、年末調整の際に証明書を会社に提出することで、所得税が控除されます。地震保険は5万円まで控除対象となっています。
また、生命保険は2012年1月1日以降に加入した場合は2万円、それ以前に加入している場合は25,000円まで全額控除されます。ただし、全額控除の対象となる金額を超えた場合は、区分によって控除される上限が定められているため、必ずしも年間で支払った保険料の全額が、控除になるわけではありません。
年末調整の時期に合わせて、加入している保険会社から証明書類が送られてくるため、会社に忘れずに提出しましょう。
節税対策5:医療費控除
会社員やサラリーマンは、1月1日〜12月31日までの1年間で支払った医療費が高額だった場合、所得控除が受けられます。最高200万円まで控除が受けられるため、場合によっては大幅な節税につながります。
この医療費控除は本人だけでなく、配偶者やその他親族の医療費も対象となります。
控除される金額は「実際に支払った医療費の合計-保険金などで補填される金額-10万円」で計算できます。ただし、年収が200万円未満の場合は、10万円ではなく、総所得金額の5%の金額になるため、注意しましょう。
節税対策6:住宅ローン控除
将来住宅の購入を考えている人は、住宅ローンを利用することで、住宅借入金などの特別控除が利用できます。住宅ローン控除は、新居の購入はもちろん、自宅の改築などの費用も対象です、
ただし、年間の所得が3,000万円以下だったり、10年以上のローン契約が必要などさまざまな条件があるため注意しましょう。事前に詳細をしっかり確認してから申請しましょう。
節税対策7:離婚または死別した時
配偶者が離婚や死別した場合は、寡婦控除・寡夫控除を受けられます。
寡婦控除・寡夫控除は、シングルマザ〜やシングルファザーに対しての税金を安くする制度です。ただし、控除される金額は、配偶者と離婚か死別かや、該当者の性別や年収によって異なるため、事前にチェックしましょう。
節税対策8:災害・盗難にあった時
災害や盗難の被害があった場合は、雑損控除と災害減免法による税金の軽減・免除の2種類の控除が受けられます。
雑損控除は、住宅、家財、衣服などの生活に必要な財産や、住宅の取り壊し費用などの災害に関連して、やむなく支出した費用なども「災害関連支出」として控除の対象となるため、確定申告のときには領収書が必要です。
この控除を受けるには被害に合ったのが通常の生活に必要な財産であり、損害の原因が震災や火災、盗難、横領でなければいけないので、自宅でなく別荘で被害があった場合や、骨董品や貴金属などが被害に合っても、雑損控除は受けられません。
また、保険で賄えるモノは対象になりませんが、保険金以上の損害が発生している場合は、控除対象となります。雑損控除は会社で行われないため、自分で確定申告を行わなければいけません。
災害減免法による税金の軽減・免除を受ける場合にも確定申告が必要のため、忘れないようにしてください。
節税対策9:株取引で損をした時
株取引を行っている人は、上場株式などの売買損失を配当所得と相殺できます。また、売買損失は3年間まで繰り越せるため覚えておきましょう。
たとえば、2018年に50万円損した場合は、2021年までにトータルで50万円以上の利益が発生しなければ、相殺できます。株取引は損失分も計算に入れておかないと利益分のみ税金がかかってしまうため、しっかりと損益を計算して、確定申告しましょう。
節税対策10:特定支出控除の特例を活用する
サラリーマンが自分で必要経費を払った場合、給与所得から差し引く事ができる「特定支出控除」の特例があります。
特定支出控除が適用されると、給与所得控除を超えた部分の支出が特定のモノに当たる場合に、必要経費として認められます。ただし、特定支出控除を受けるためには、必要経費が給与所得控除額の50%を超えていなければいけません。
特定支出控除を受けることで、以下のような計算式となります。
- 原則:給与総額-給与所得控除額=給与所得
- 特定支出控除の特例:給与の総額-(給与所得控除+特定支出のうち給与所得控除額の1/2を超える部分)=給与所得
たとえば、年収400万円の人の場合、給与所得控除額は「400万円×20%+ 44万円=124万円」となるので、124万円の50%である62万円を必要経費で支払っていなければいけません。また、特定支出は会社や企業などの給与支払者が証明したものに限定されるため、注意しましょう。
特定支出とは以下のような支出になります。
- 通勤費
- 転居費
- 研修費
- 資格取得費
- 帰宅旅費
節税対策11:共働き夫婦は扶養控除のつけ方に注意する
高校生以上の子供を扶養している場合は、所得税と住民税を計算するときに扶養控除を受けられるため、支払う税金を抑えられます。ただし、共働きの家庭の場合は所得税は収入が高くなると税率が高くなるため、収入の高いほうに扶養控除を受けましょう。
扶養控除は親と一緒に住んでいる家族全体の生活費を負担している場合であっても受けられます。そのため、両親が65歳以上で年金生活をしていて、年金受給額がひとりあたり158万円以下の場合は、扶養に入ります。
たとえば、年収600万年の人が60代後半の親を扶養に入れれば、 所得税と住民税が年7万円も安くなります。しかも、親の年齢が70歳以上になると、扶養控除の金額も更に増えるため、さらなる節税が期待できます。
扶養控除が受けられるかどうか以下の項目から確認しましょう。
- 配偶者以外で16歳以上の6親等内の血族および3親等内の姻族であること
- 生計を一つにしていること
- 扶養親族の年間の合計所得金額が48万円以下であること
- 青色や白色の事業専従者でないこと
- 申告者本人以外の扶養親族や控除対象配偶者ではないこと
- 12月31日時点で満たしていること
ただし、扶養親族の合計所得が48万円以下とは、アルバイトやパートで働いている場合は、年収103万円以下、65歳以上で年金の収入のみの場合は、年収158万円以下となるため注意しましょう。
副収入は節税できるのか?
最近では副業が人気となっています。会社員として働いている人でも、副業で収入を得ている人も多いですが、副収入も確定申告しなければいけません。
青色申告なら最大65万円の特別控除が受けられる
青色申告であれば、最大で65万円の特別控除が受けられますが、特別控除を受ける場合は、開業届と青色申告承認申請書を、税務署に提出する必要があります。
事業所得として申告することで、確定申告の際に最大650,000円の特別控除を受けられます。ただし、副業の規模によっては事業所得と認められずに、雑所得として申告しなければいけないと、税務署から指導を受ける場合があります。
この場合は、青色申告特別控除が受けられないため、注意しましょう。会社によっては企業が禁止にしている場合もあるため、副業を行う際はトラブルを避けるためにも、事前に勤務先に確認しておくと安心です。
間違った税金対策を行うと罰則を受けることに
本業でも副業であっても収入を得た場合、必ず納税しなければいけません。フリーランスや自営業で生計を立てている人は、必ず確定申告を行います。
しかし、会社員やサラリーマンの人は会社が自動で行っているため、副業で稼いだ金額の申告を忘れてしまう人も多くいます。
確定申告を行わなかったり、架空の経費を計上したりする事は、実際と異なる収入を申告することになり、違法になります。うっかりミスで所得の操作を行ってしまった場合でも、税務署が脱税で判断すれば罰則を受けることになります。
たとえば、税金を期限までに集めなかったり、期限後の申告、修正申告を行ったりすると、延滞税が発生します。他にも、以下のような加算税が課せられる場合もあるため、注意しましょう。
| 加算税名 | 詳細 |
| 過少申告加算税 | 申告期限内に申告したが、納税額が過小だった場合に加算される。 最大15%課税。 |
| 無申告加算税 | 申告期限までに申告しなかった場合に加算される。原則として、納付すべき税額に対して、50万円までは15%、50万円以上の場合は20%になる。 ただし、自主的に期限後申告を行った場合は、5%に軽減される。 |
| 不能化加算税 | 源泉徴収を行わなければならない人物が源泉所得税を納付期限までに納付しなかった場合に加算される。 課税割合は10%。 |
| 重加算税 | 虚偽の収入申告をしたり、隠蔽したりなどをした場合、加算される。 課される税率も高く、最大40%。 |
実はサラリーマンは太陽光投資の節税対策が効果的!
太陽光投資は、太陽光をエネルギーとして発電した電気を電力会社に買い取ってもらうことで利益を出す投資方法です。ひと昔前に流行り、今では「オワコン」「もう儲からない」といった口コミを耳にする機会がありますが、実は不動産投資をしていた人が太陽光投資に乗り換えたり、不動産投資と一緒に運用したりするパターンがここ最近で急増しています。
太陽光投資は不動産投資と違って、国が定めた制度のもと運用する投資なので、買取金額が一定の期間変わることがありません。
そのため、不動産投資のように空き家リスクが生じたり、世の中の経済状況によって左右されることがありません。そのため、ローリスク〜ミドルリスクでハイリターンの投資方法だと投資経験者から人気を集めているのです。
また、不動産投資の場合ローンを借りる際に頭金や担保が必要になるケースが多いですが、太陽光投資は頭金・担保・貯金が少なくても、ローン審査に通る可能性が高い点がメリットです。
詳しい太陽光投資と不動産投資の比較については、こちらの記事で説明しています。また、詳しい節税内容は、太陽光発電売買仲介の『SOLSEL』では、無料で太陽光投資セミナーを実施しているので、興味がある方は参加してみることをおすすめします。
会社員(サラリーマン)の節税に関するQ&A
サラリーマンが節税を行う際の疑問を解説します。
会社員が節税を始めたほうが良いのは年収いくらから?
令和2年からは、給与所得控除が引き下げられていることもあり、会社員が節税を始めたほうが良いのは、年収300万円くらいからです。
年収が800万円を超えると、会社員は増税対象となってしまうため、より節税を考えることをおすすめします。
会社員でも投資を考えたほうが節税になる?
不動産投資などで、会社員でも節税ができます。不動産投資の場合は、最初に不動産の購入を行うため、初年度は赤字になってしまう場合が多いですが、サラリーマンなら、不動産投資で生じた赤字を給与所得の課税所得額から控除する「損益通算」が可能です。
給与所得より不動産投資の赤字分を差し引くと、課税所得額が低くなるため、節税に繋がります。
会社員が節税のために会社を設立するのは意味ある?
会社員が不動産投資などを行っている場合、会社を設立することで、節税できる場合があります。例えば、本人・家族への役員報酬で節税ができたり、消費税の納税義務が免除されるため、節税ができます。
ただ、勤務している会社が会社設立を就業規則で禁止している場合もあるので、注意が必要です。
まとめ
今回は会社員やサラリーマンでも簡単にできる節税方法を紹介しました。特に、ふるさと納税やiDeC、NISAは簡単に節税できるため、非常に人気がある節税方法です。
ただし、確定申告を行わなかったり、架空の経費を計上したりなどの間違った税金対策を行うと、罰則を受ける可能性があります。正直に申告しつつ、できる節税対策から取り入れていきましょう。